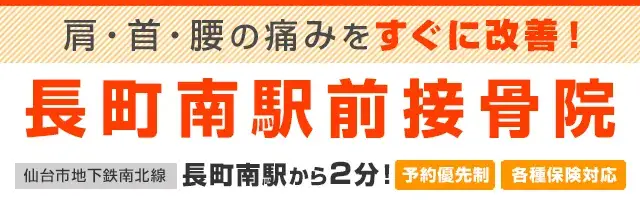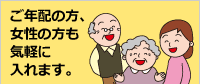肉離れ


こんなお悩みはありませんか?

普段の生活の中でこんなお悩みはありませんか?
身体が硬く、筋肉が硬い
筋肉が疲れている、重ダルさを感じる
運動中に脚などに急に激痛が走った
『プチッ』と筋肉が切れたような音がした
脚がよくつる
冷え性
など、上記のようなお悩みがありましたら『肉離れ』になる可能性があります。
肉離れはジャンプやダッシュなど急激に筋肉に負荷がかかる動作をした際に起こりやすく、発症すると激痛が走り、運動どころか歩行も難しくなります。ウォーミングアップをせずに運動を始めたり、筋肉が硬く疲労していたりすると肉離れを起こしやすくなります。
身体に違和感や痛みを感じましたらお早めに当院へご連絡・ご来院下さい!
肉離れで知っておくべきこと

肉離れで知っておくべきことは、肉離れがどういうものなのかです。
肉離れとは俗称で、正式には「筋挫傷(きんざしょう)」といいます。スポーツを行う中で、急に無理な動作をした場合に発生する筋膜や筋繊維の損傷・断裂を指します。筋肉が裂けたり破れたりすることを筋断裂といいますが、筋断裂のうち、範囲が部分的なものを一般的に肉離れと呼びます。
発症すると患部に激痛が走り、それ以上運動を続けることができなくなります。時には筋肉が断裂した瞬間に「プチッ」という音が聞こえることもあります。また、痛みのある部位をよく観察すると、くぼみや変色が生じている場合もありますが、これは個人差によって異なります。
症状の現れ方は?

肉離れの症状の現れ方としては、ジャンプやダッシュなどの急激に筋肉に負荷がかかる動作を行った際に、負荷がかかった筋肉が裂けたり、切れたり、断裂することによって炎症や内出血を引き起こし、患部が腫れ、激しい痛みを感じます。部分的に断裂することが多いですが、稀に筋肉が完全に断裂することもあります。また、筋肉が断裂した瞬間に『プチッ』という筋肉が切れる音が聞こえることもあります。
肉離れを起こした部分をよく観察すると、くぼみや肌が変色している場合もありますが、これは個人差によって異なります。肉離れを発症すると、激しい痛みにより運動が続けられなくなったり、歩行が難しくなることがあります。
その他の原因は?

肉離れが起こる原因としては、筋肉に急激な負荷がかかり、筋肉が耐えられなくなったときに起こります。主な原因としては
・急なダッシュやジャンプ、ストップなどの動作
・筋肉の疲労
・筋力の低下
・柔軟性の低下
・ウォーミングアップ不足
・水分不足や飲酒による脱水症状
・冬場の冷え
などがあります。肉離れは、スポーツ中や肉体労働中に起こりやすいですが、筋肉が疲れていたり、筋力が低下している場合や、準備運動不足の場合にも起こり得ます。また、筋肉が硬いまま運動をすると肉離れのリスクが高くなります。
肉離れが起こる前兆として、筋肉が硬くなってこわばった感じがしたり、太ももに違和感を覚えたりするケースが多くみられます。受傷した瞬間に激しい痛みを感じて、それ以上動けなくなります。肉離れを予防するには、日頃からストレッチをするなどして筋肉を柔らかい状態にしておくことが大切です。
肉離れを放置するとどうなる?

肉離れを放置すると、以下のようなリスクや問題が発生する可能性があります。
1. 回復の遅れ
適切な施術を受けないと、自然に回復するまでに非常に長い時間がかかることがあります。筋肉が完全に回復しないまま再び負荷をかけると、再発や悪化のリスクが高まります。
2. 筋力低下
放置すると、損傷した筋肉が適切に回復せず、筋力低下が生じることがあります。これにより、日常生活や運動能力に影響を与えることがあります。
3. 慢性的な痛みや不調
肉離れを施術せずに放置すると、損傷部位に慢性的な痛みや炎症が残ることがあります。また、姿勢や動作のバランスが崩れ、他の部分にも負担がかかることがあります。
4. さらなる損傷
完全に回復していない状態で無理に動かすと、筋肉が再度損傷し、より深刻な怪我に発展するリスクがあります。
当院の施術方法について

当院の施術方法は
1. 初期施術(RICE処置)
初期の段階では、RICE処置が中心となります。これは、損傷直後に筋肉の損傷を抑えるための基本的な方法です。
・Rest(安静)
損傷した部位を休ませ、さらに悪化しないようにします。
・Ice(冷却)
炎症や腫れを抑えるために、患部を冷やします。1回あたり15~20分、1日に数回行います。
・Compression(圧迫)
包帯やサポーターを使って患部を圧迫し、腫れを防ぎます。
・Elevation(挙上)
損傷部位を心臓より高く保つことで、血流を抑え、腫れを軽減します。
2.電気療法(低周波・干渉波)
電気刺激を筋肉に与えて、痛みの軽減や筋肉の緊張を和らげる施術法です。損傷部位周辺の筋肉の硬直を緩め、回復を促進することができます。
3.手技療法(マッサージ・筋膜リリース)
専門的な手技を使って筋肉の緊張をほぐし、血流を促進する方法です。損傷周辺の筋肉や筋膜に対するマッサージやストレッチを行い、痛みの軽減や回復をサポートします。ただし、損傷がひどい場合は、直接のマッサージは避け、間接的なアプローチをしていきます。
4.テーピングやサポーターの使用
筋肉を安定させ、動きをサポートするためにテーピングを行います。特にスポーツを行う際や日常的な動作で再発を防ぐ目的で使用していきます。
5.リハビリ指導
痛みが和らぎ、ある程度の回復が見込めた段階で、徐々に筋力を回復させるためのストレッチや軽い運動、筋力トレーニングなどを通じて、再発を防ぐための体作りを行います。
6.温熱療法
急性期を過ぎた後、血流の改善や筋肉の柔軟性を高めるために温熱療法を行います。ホットパックや赤外線などを使用して、筋肉の回復をサポートします。
改善していく上でのポイント

肉離れを改善していくためのポイントは
1. 早期対応(RICE処置)
怪我をした直後は、RICE処置を行うことが大切です。
・安静
怪我した部分を動かさないようにする。
・冷却
冷やすことで炎症や腫れを防ぎます。
・圧迫
サポーターや包帯で患部を軽く圧迫し、腫れを抑えます。
・挙上
足や腕などの損傷部位を心臓より高く保ち、腫れや内出血を抑えます。
2. 無理をしない
痛みが軽減しても、無理をしてすぐに運動や負荷の高い活動を再開するのは避けましょう。肉離れが完全に治っていない状態で負荷をかけると、再発や悪化するリスクが高くなります。医師や接骨院の指示に従い、少しずつ運動を再開することが大切です。
3. リハビリの重要性
筋肉の損傷が回復してくると、徐々にリハビリが必要になります。特に以下の点に注意しましょう。
・柔軟性の回復
損傷した筋肉やその周辺の筋肉をストレッチして、柔軟性を取り戻すことが大切です。
・筋力トレーニング
徐々に筋力を強化することで、再発を防ぎます。最初は軽い負荷から始め、筋肉にかかる負荷を徐々に増やしていきます。
4.適切な休息と睡眠
筋肉の回復には、適切な休息と十分な睡眠が不可欠です。睡眠中に体は損傷を修復し、再生を促進します。睡眠不足は回復を遅らせるため、怪我の際は特に気をつけて十分な睡眠を確保しましょう。
5.適切なサポートアイテムの使用
テーピングやサポーターを使って、負荷がかかりやすい筋肉や関節をサポートしましょう。特に運動を再開する際には、サポートアイテムを使用することで、再発のリスクを軽減できます。
6.ストレス管理
慢性的な疲労やストレスは、怪我の回復に悪影響を与えることがあります。精神的なストレスを軽減し、リラックスすることも回復に役立ちます。瞑想や深呼吸など、ストレスを緩和する方法を取り入れてみてください。
段階的に筋肉を回復させることで、再発を防ぎながらしっかりと治していくことが可能です。
監修

長町南駅前接骨院 院長
資格:柔道整復師
出身地:山形県山辺町
趣味・特技:映画鑑賞、温泉、サウナ