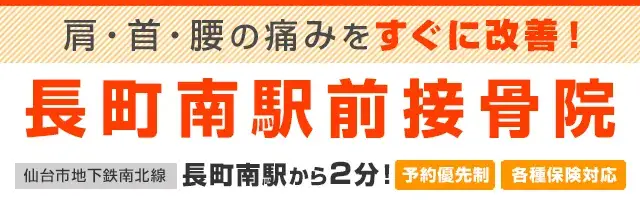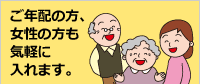巻き肩


こんなお悩みはありませんか?

肩こりや首の痛みがある
呼吸が浅いと感じることがある
姿勢が悪く見える
肩や背中の筋力低下を感じる
肩が動きにくいと感じる
巻き肩は適切なエクササイズや姿勢を意識することで予防や軽減が期待できますので、早めに対策を取ることが大切です。
巻き肩について知っておくべきこと

巻き肩(まきがた)は、肩が前に巻き込んでしまう姿勢のことを指し、現代の生活習慣、特に長時間のデスクワークやスマホ使用によって多くの人に見られる傾向があります。巻き肩になると、肩こりや首の痛み、背中の張りなどを引き起こすことがあります。
巻き肩を軽減するために知っておくべきポイントは以下の通りです。
1. 原因を理解する
姿勢の悪さ:長時間の前かがみ姿勢や猫背が巻き肩の原因になります。特にパソコンやスマホを見るとき、肩が前に出てしまうことが多いです。
筋力不足:背中や肩甲骨周りの筋肉が弱くなることで、肩が前に巻きやすくなります。一方で、胸の筋肉が縮みすぎることも巻き肩を悪化させる要因です。
2. 肩周りの筋肉を強化する
背中や肩甲骨周りの筋肉を強化するエクササイズが効果が期待できます。例えば、肩甲骨を寄せるエクササイズやプッシュアップ(腕立て伏せ)などがあります。
3. 姿勢を意識する
座っているときや立っているときに、肩を後ろに引いて胸を張るように心がけましょう。デスクワークの際はモニターの高さや椅子の位置を調整し、前かがみにならないように意識します。
4. ストレッチで柔軟性を保つ
胸の筋肉(大胸筋)を伸ばすストレッチや、肩甲骨周りの柔軟性を高めるストレッチを定期的に行うことで、姿勢の軽減が期待できます。
5. 意識的な休憩と動作
長時間同じ姿勢を続けないように、定期的に休憩を取り、肩を回したり、体を伸ばしたりすることが大切です。
6. 巻き肩の進行を防ぐ
巻き肩がひどくなる前に、早めに対処することが重要です。痛みが出る前に予防策を講じることが、軽減につながります。
巻き肩を軽減するには、日々の習慣が大きく影響します。気づいた時に姿勢を直したり、エクササイズやストレッチを取り入れていくことが大切です。
症状の現れ方は?

巻き肩(まきがた)とは、肩が前方に巻き込むような姿勢になる状態のことを指します。この状態の現れ方としては、以下のようなものがあります。
1. 肩の前方への突出
肩が前に出て、胸が縮こまるような姿勢になることがあります。これにより、背中が丸く見えたり、猫背になったりします。
2. 肩や背中の痛み
肩が巻き込むことで、肩周りや背中、首の筋肉が緊張し、痛みや不快感を感じることがあります。
3. 肩こり
肩が前方に引っ張られることで、肩甲骨の動きが制限され、血流が悪くなり、肩こりを引き起こすことがあります。
4. 腕や手のしびれ
巻き肩により肩の筋肉が硬直し、神経が圧迫されることがあります。これにより、腕や手にしびれや違和感を感じることがあります。
5. 呼吸が浅くなる
胸の筋肉が圧迫されることで、呼吸が浅くなることがあり、息苦しさを感じることがあります。
6. 姿勢の悪化
巻き肩の状態が進行すると、姿勢が悪化し、さらに肩や背中に負担がかかりやすくなります。
巻き肩の原因には、長時間のデスクワークやスマートフォンの使用、姿勢の悪さなどが影響していることが多いです。軽減方法としては、姿勢の矯正や肩周りのストレッチ、筋力強化が効果が期待できます。
その他の原因は?

巻き肩は、肩が前方に丸まった姿勢を指し、主に次のような原因で引き起こされることが多いです。
1. 姿勢の悪さ
長時間のデスクワークやスマホの使用、パソコン作業などが原因で、肩が前に出てしまう姿勢が続くと、巻き肩が進行することがあります。
2. 筋力の不均衡
胸筋が過剰に発達している一方で、背中や肩甲骨周りの筋肉(特に肩甲骨を引き寄せる筋肉)が弱くなると、肩が前に引っ張られやすくなります。
3. ストレスや緊張
ストレスや不安が原因で肩に力が入ると、肩が前に出た状態で固まりやすくなります。
4. 運動不足
特に背中の筋肉を使う運動が少ない場合、肩甲骨周りの筋肉が弱くなり、巻き肩が進行します。
5. 不適切な寝具や座椅子の使用
寝具が合わない、または座椅子で不自然な姿勢を続けると、肩に負担がかかりやすくなります。
巻き肩は、肩や背中の痛み、頭痛、肩こりなどを引き起こすことがありますので、適切な姿勢を保つことや筋力トレーニング、ストレッチが予防や軽減に役立ちます。
巻き肩を放置するとどうなる?

巻き肩(肩が前に丸まった姿勢をとること)は、放置するといくつかの体調不良を引き起こす可能性があります。以下のような影響が考えられます。
1. 姿勢の悪化
巻き肩が続くことで、猫背や肩こり、首の痛みを引き起こしやすくなります。姿勢が悪くなると、身体全体のバランスが崩れ、長期的には骨や関節に負担がかかります。
2. 肩や背中の筋肉の緊張
巻き肩によって、肩甲骨周辺や背中の筋肉が常に引っ張られ、過緊張状態になります。これが慢性的な筋肉のこりや痛みを引き起こすことがあります。
3. 呼吸への影響
丸まった肩の姿勢は胸部を圧迫し、呼吸が浅くなることがあります。長期的には呼吸効率が低下し、酸素供給が不十分になる可能性があります。
4. 神経や血管への圧迫
巻き肩がひどくなると、神経や血管が圧迫されることがあります。これが手のしびれや、腕の痛み、血行不良を引き起こすことがあります。
5. 頭痛や肩こり
巻き肩が続くと、首や肩の筋肉に負担がかかり、頭痛や肩こりを引き起こすことがあります。
当院の施術方法について

巻き肩(肩が前に丸まってしまう状態)は、姿勢の悪さや筋力の不均衡が原因で起こることが多いです。この状態を軽減するための当院の施術方法は、全身骨格矯正をお勧めしております。
1. 姿勢の意識づけ
肩甲骨の寄せ:両肩を後ろに引いて、肩甲骨を寄せるストレッチを行います。これにより、肩周りの筋肉が強化され、巻き肩の軽減が期待できます。
2. 胸部のストレッチ
胸の筋肉(大胸筋)をストレッチして柔軟性を高めることで、肩が前に引き寄せられるのを防ぐことができます。
3. 姿勢改善の指導
巻き肩は不良姿勢が原因となることが多いため、姿勢改善の指導が行われます。背筋を伸ばし、肩甲骨を寄せる意識を持つようにします。
4. ストレッチと運動指導
肩周りの筋肉を柔軟に保つために、胸筋や肩甲骨周りの筋肉をストレッチする方法や、肩甲骨を正しい位置に戻すためのトレーニングを指導します。
軽減していく上でのポイント

巻き肩を軽減するためのポイントは以下のようになります。
1. 姿勢を意識する
姿勢を整えることが最も大切です。普段から肩を後ろに引き、背筋を伸ばす意識を持ちましょう。座っている時や立っている時に、肩が前に出てしまわないように気をつけることが重要です。
2. 肩甲骨を寄せるエクササイズ
肩甲骨を寄せる運動をすることで、背中の筋肉(特に僧帽筋)を強化します。例として、肩甲骨を寄せて引く「肩甲骨の内転運動」や、手を肩の高さに持ち上げて肩甲骨を引き寄せる運動があります。
3. 胸筋をストレッチする
巻き肩は胸筋の硬さが原因になることがあります。胸を開くストレッチや、肩の前側の筋肉を伸ばすストレッチを行うことで、肩の前側が緩み、巻き肩の軽減が期待できます。具体的には、壁に手をついて胸を伸ばすストレッチなどがあります。
4. 背筋を鍛える
背中の筋肉(特に広背筋や脊柱起立筋)を強化することも有効です。背筋を鍛えることで、肩が自然と後ろに引かれやすくなります。おすすめは、ラットプルダウンやロウイングなどの背中を鍛えるトレーニングです。
5. デスクワークの姿勢を改善する
デスクワークやスマホの使用などで巻き肩が悪化することが多いため、作業中は背筋を伸ばし、モニターの位置を目線と合わせ、肩が前に出ないようにしましょう。
6. 定期的なストレッチと休憩
長時間同じ姿勢でいると肩が固まってしまうので、1時間ごとにストレッチをして肩をリセットすることが効果的です。
これらを日常的に意識し、少しずつ実践していく
監修

長町南駅前接骨院 院長
資格:柔道整復師
出身地:山形県山辺町
趣味・特技:映画鑑賞、温泉、サウナ